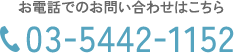- 交通事故に遭われた方へ
- このような症状はありませんか?
- 交通事故後の治療までの流れ
- 交通事故に関する治療費について
- 交通事故に関するよくある質問
- 仕事中や通勤中の怪我に対する労災保険について
- 労災に関するよくある質問
交通事故に遭われた方へ
交通事故後の症状は遅れて出ることがあります
 交通事故直後は緊張や興奮によって、痛みや違和感を感じにくいことがあります。数日経ってから首や腰、肩、関節などに痛み・しびれ・重だるさが出てくるケースは珍しくありません。特に「むち打ち症」は事故直後には軽度でも、時間の経過とともに悪化することがあります。
交通事故直後は緊張や興奮によって、痛みや違和感を感じにくいことがあります。数日経ってから首や腰、肩、関節などに痛み・しびれ・重だるさが出てくるケースは珍しくありません。特に「むち打ち症」は事故直後には軽度でも、時間の経過とともに悪化することがあります。
放置すると慢性化や後遺症につながる恐れがあるため、できるだけ早期の受診をおすすめします。
交通事故に遭われた方の診療につきましては、事故との因果関係を明確にするため、
初診は事故発生後2週間以内に受診された方のみを対象とさせていただきます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
当院で行う検査と診断
当院では、まず医師による丁寧な問診と触診で症状や事故状況を確認します。必要に応じて X線(レントゲン)検査 を行い、骨折や脱臼の有無を確認します。さらに、必要に応じてMRIや超音波検査などを追加しています。
画像所見と臨床症状を総合的に判断し、患者様一人ひとりに合わせた治療方針をご提案します。
治療の流れ
- 薬物療法:消炎鎮痛薬などで炎症や痛みを抑えます。
- リハビリテーション:理学療法士による運動療法を通じて、機能回復と再発予防を図ります。
- ブロック注射:強い痛みが持続する場合には、神経ブロック注射で症状を軽減します。
当院では、痛みの改善だけでなく、早期回復と再発防止までを視野に入れた治療を行っています。
受診を迷われている方へ
「大したことがないと思っていたのに、数日後から痛みが強くなってきた」
「検査を受けて安心したい」
「後遺症が残らないか心配」
こうした不安を抱えている方は、ぜひお早めにご相談ください。事故直後の早期対応が、その後の回復に大きく影響します。
このような症状はありませんか?
交通事故後、次のような症状がある場合、時間の経過とともに悪化する恐れがあります。気になる症状があれば、当院へ早めにご相談ください。
- 頭痛
- 手足のしびれ
- 背中や腰、膝の痛み
- 関節の動かしにくさやこわばり
- むち打ち症が疑われる症状(首の痛み、耳鳴り、吐き気、めまいなど)
- その他、身体の部位に感じる痛みや違和感、しびれなど
交通事故後の治療までの流れ

1保険会社への連絡
交通事故に遭われた際は、まずご加入の保険会社に連絡し、当院での受診を希望される旨をお伝えください。保険会社から当院へ治療依頼の連絡が入ることで、自己負担なく治療を受けて頂けます。
2事故状況と症状の確認
ご来院後、スタッフが事故の内容や現在の症状についてお伺いします。
3医師による診察
 医師が症状を確認し、必要に応じてX線(レントゲン)検査やエコーなどの検査を行います
医師が症状を確認し、必要に応じてX線(レントゲン)検査やエコーなどの検査を行います
4X線(レントゲン)検査、エコー検査の実施
 骨折や骨の異常の有無を確認するため、X線撮影を行います。また関節周囲等の軟部組織の評価目的にエコー検査も行います。
骨折や骨の異常の有無を確認するため、X線撮影を行います。また関節周囲等の軟部組織の評価目的にエコー検査も行います。
5治療方針のご説明・決定
診察と検査結果をもとに、今後の治療計画についてご説明し、ご相談しながら方針を決定します。
6リハビリの開始
 症状の悪化を防ぎ、早期回復を図るため、できるだけ早い段階からリハビリをスタートします。各患者様の症状に合わせて、理学療法士やセラピストがプランを立て、適切なリハビリを実施します。定期的に画像チェックを行うことで治療の効果や経過を正確に把握し、必要に応じてリハビリプランの見直しや治療方針の調整を行います。
症状の悪化を防ぎ、早期回復を図るため、できるだけ早い段階からリハビリをスタートします。各患者様の症状に合わせて、理学療法士やセラピストがプランを立て、適切なリハビリを実施します。定期的に画像チェックを行うことで治療の効果や経過を正確に把握し、必要に応じてリハビリプランの見直しや治療方針の調整を行います。
交通事故に関する治療費について
自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険で、交通事故の被害者を救済することを目的としています。加害者の経済状況にかかわらず、被害者は最低限の補償を受けることが可能で、加害者側の自賠責保険に対して請求が可能です。
当院では、健康保険あるいは自費による治療にも対応しており、健康保険を利用する場合には、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出することで適用が可能です。その後、保険組合が加害者側に医療費の請求を行います。
治療費の取り扱い
加害者・被害者どちらも損害保険の使用に合意している場合には、患者様の自己負担なく治療を受けて頂けます。
交通事故に関するよくある質問
通院にあたってどのような手続きが必要ですか?
当院での治療を希望される場合は、まずご加入の保険会社へご連絡頂き、当院を受診する旨をお伝えください。保険会社から当院に連絡が入れば、治療費は自己負担なく受けて頂けます。
なお、保険会社への連絡前に受診された場合は一時的に費用をご負担頂きますが、後日保険会社から連絡があれば、お支払い頂いた分を返金いたします。
他の病院で治療中ですが、転院は可能ですか?
転院は可能です。現在通院中の医療機関で紹介状を発行してもらい、当院までお持ちください。また、スムーズな手続きのために、事前に保険会社へ転院の旨をご連絡頂くようお願いいたします。
数日経ってから痛みが出てきましたが、治療を受けられますか?
はい、治療可能です。交通事故では、事故直後に自覚症状がなくても、数日後に痛みや違和感が出てくることがあります。わずかな変化でも構いませんので、お早めにご相談ください。
診断書や各種証明書の発行は可能ですか?
交通事故に関する診断書や証明書の発行にも対応しております。必要な書類についてはお気軽にご相談ください(文書発行には別途費用がかかります)。
治療はいつまで受けられますか?補償や慰謝料についても教えてください。
保険会社から治療終了の連絡があるまでは、費用の自己負担なしで通院を続けて頂けます。万が一、後遺症が残った場合には「後遺障害診断書」が必要となり、この診断書をもとに補償費や慰謝料の請求が可能です。当院でも診断書の作成・発行を行っております(文書料は別途かかります)。
仕事中や通勤中の怪我に対する労災保険について
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中の事故による労働者の怪我や病気、後遺症が残る、亡くなった場合に備えて、労働者本人やその遺族を保護するための制度です。当院では、労災保険法に基づいた診療・治療を行っております。
業務中の災害
労働基準法では、勤務中の事故により発生した怪我や病気、障害、死亡に対して、雇用主が補償を行うことが義務づけられています。対象となる「労働者」には、正社員だけでなく、派遣社員やパート、アルバイトも含まれます。
また、労働者の不注意による事故であっても、業務中の災害であれば労災保険の適用対象となります。
通勤中の災害
通勤中に起こった事故が原因で怪我や病気を負った場合も、労災保険の対象となります。ここでいう「通勤」とは、住居と職場との往復や業務上必要な移動を指し、私的な用事によって通勤ルートから外れた場合などは対象外となります。
ただし、日常生活に必要とされる範囲で行われた行為であれば、一定の条件下で適用されることがあります。例えば、通勤途中の日用品の購入、業務に関係する学校への通学、選挙での投票、医療機関への受診などが該当します。
労災に関するよくある質問
初診時に必要な持ち物はありますか?
受診時には、勤務先から交付された労災関連の書類をご持参ください。
通勤災害の場合は「様式第16号の3」、業務災害の場合は「様式第5号」が必要です。なお、公務員の方は別途定められた様式をご用意頂く必要があります。
万が一、緊急時などで書類をお持ちでない場合は、初回のみ治療費を一時的にご負担頂きますが、後日書類をご提出頂ければ返金いたします。
労災での治療は自己負担になりますか?
労災保険が適用された場合、患者様の治療費の自己負担はありません。
ただし、労災として認定されるまでの間は健康保険での対応となり、一時的に費用をお支払い頂くことがあります。労災認定後は、既に支払われた治療費が返金されます。
なお、災害が労働者の不注意によって起きた場合でも、業務との関連性が認められれば労災保険の対象になります。最終的な認定は労働基準監督署が行います。
後遺障害診断書の作成は可能ですか?
労災による障害補償給付を申請する際には、労働基準監督署に提出する申請書と併せて「後遺障害診断書」の提出が必要です。この診断書は医療機関が作成するもので、当院でも対応可能です(文書料は別途かかります)。診断書の内容をもとに、後遺障害の有無や程度が審査されます。