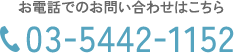テニス肘について
— 手首や肘の痛み、家事やスポーツ時の肘の違和感にお悩みの方へ —
テニス肘とは?
 テニス肘とは、正式には上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)と呼ばれ、肘の外側にある腱の炎症により痛みが生じる疾患です。
テニス肘とは、正式には上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)と呼ばれ、肘の外側にある腱の炎症により痛みが生じる疾患です。
テニス愛好家の多くが発症することから「テニスエルボー」として知られていますが、実際にはテニスをしていない人にも頻発します。
日常生活や仕事で手首を酷使する動作(ものを持つ、ひねる、絞るなど)を繰り返すことが原因となり、主婦の方、調理師、美容師、ゴルファー、デスクワークの多い方にも多く見られます。
テニス肘の原因
手首の使いすぎ(オーバーユース)
 テニス肘は、手首を反らす動作を繰り返すことで、肘の外側にある手関節伸筋群の付着部に負荷がかかり、炎症が起こることで発症します。
テニス肘は、手首を反らす動作を繰り返すことで、肘の外側にある手関節伸筋群の付着部に負荷がかかり、炎症が起こることで発症します。
特にテニスプレーヤーの場合、ラケットでボールを打つ際のインパクトによって手首に強い力が加わり、筋肉が強く収縮するため、繰り返す動作によって負担が蓄積します。特にバックハンドストロークの動作ではこの部位を酷使するため、強い痛みが現れやすい傾向があります。
週3回以上の頻度でテニスを行う方は、発症のリスクが高まるという報告もあり、多くのケースは「腕の使いすぎ」が原因です。
特に初心者〜中級者では、ラケットの面で正確にボールを捉えられずに負荷がかかる場合や、ラケットの素材やガットの硬さ、衝撃吸収性などが影響して痛みを引き起こすこともあります。
このような「同じ動作を反復することで起きる怪我」はスポーツ障害の一種であり、テニスの他にも、バドミントン、卓球、ゴルフなど、手首を多用する競技においても多く見られます。
加齢に伴う筋腱組織の変性
40代以降でテニス肘を発症する人が増えることから、年齢的な変化も要因の1つと考えられます。
加齢により筋肉や腱の柔軟性が低下すると、同じ動作でもダメージが蓄積しやすくなり、微細な損傷が生じやすくなります。
手首を使う頻度や強度が変わらなくても、年齢を重ねるほど痛みを感じやすくなるのはこのためです。
また、性別に関係なく発症しますが、筋力の面や腕を使う機会が多いことから、特に40〜60代の女性、主婦の方に多く見られる傾向があります。家事による反復動作も、テニス肘の発症に関与していると考えられています。
テニス肘の主な症状
テニス肘では、手首に負担のかかる動作をした際に、肘の外側に痛みが生じやすくなります。特に、手首を反らすような動きや、物を掴んで持ち上げるときに症状が顕著に現れるのが特徴です。
- テニス中にスイング動作で肘が痛くなる
- ゴルフのスイング時に肘の外側に違和感がある
- ペットボトルのフタを開ける際に痛みがある
- コップを持ち上げるだけでも痛む
- ドアノブを回す、扉を開けるときに痛む
- フライパンを持つ、洗い物をするなどの家事で痛む
- 買い物袋などを持ち上げたときに痛む
- 雑巾を絞る動作で痛みを感じる
- パソコン作業中のマウス操作やキーボード入力で痛む
テニス肘の検査
診断は以下の流れで行います。
- 問診:痛みが出る動作や生活習慣を確認
- 徒手検査:トムセンテスト(手首を反らして抵抗すると痛みが出る)、チェアテスト(椅子を持ち上げると痛む)
- 画像検査:
- X線検査で骨の異常を除外
- エコーで腱の炎症や損傷を評価
- MRIで重度の腱断裂や他の疾患を鑑別
テニス肘の治療
保存療法
まずは患部を安静に保つことが大切です。痛みの原因となったテニスやその他の動作は一時的に控え、炎症が落ち着くまでは負荷をかけないようにしましょう。消炎鎮痛薬や湿布などを用いて症状を軽減させる治療を行います。
リハビリテーション
ストレッチや筋力トレーニングを通じて、手首や肘にかかる負担を減らす動作を身につけていきます。即効性はありませんが、中長期的にはリハビリが最も効果的な治療法とされています。
症状の背景にある動作や筋力のアンバランスを改善するため、理学療法士の指導のもと、姿勢や動作の見直しを図ります。必要に応じて、テーピングなどの物理療法も併用します。
薬物療法
痛みや炎症が強い場合には、ロキソニンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を服用するか、湿布を使用して炎症を抑えます。ただし、内服薬の長期使用は胃の不調などの副作用が生じることがあるため、使用期間には注意が必要です。
装具療法
肘より手首側にある伸筋腱の部分を圧迫することで、肘の外側の負担を軽減します。パッド付きのバンドを、肘の外側にある骨(上腕骨外側上顆)より指2本分ほど下の位置に装着することで、腱の付着部へのストレスを軽減します。
注射
強い痛みで日常生活や仕事に支障がある場合には、ステロイド注射を行うことがあります。炎症のある部位に直接注射することで、1〜2ヶ月程度症状が改善することもありますが、再発することもあります。
また、注射を繰り返すことで腱や周囲組織が脆くなるリスクがあるため、回数には注意が必要です。当院では、超音波ガイド下で注射を行い、必要最小限の量を正確に患部へ届けるよう配慮しています。
PRP治療
 PRP(Platelet Rich Plasma:多血小板血漿)治療は、自身の血液から血小板を抽出・濃縮し、患部に注入することで修復を促す先進的な治療法です。
PRP(Platelet Rich Plasma:多血小板血漿)治療は、自身の血液から血小板を抽出・濃縮し、患部に注入することで修復を促す先進的な治療法です。
血小板には組織の修復を促進する因子が含まれており、血流の乏しい腱やその付着部の再生を助ける効果が期待されています。この治療は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づいて実施されています。
日常生活での工夫と予防
- デスクワークでは 肘と手首の角度を正しく保つ
- パソコンのマウス・キーボード操作はこまめに休憩を入れる
- 家事では 利き手をかばいすぎず両手を使う
- テニスやゴルフでは ラケット・クラブの重さ・ガットの硬さを調整
- 使いすぎを防ぐために 日々のストレッチ習慣 を身につける
当院での対応
当院では、画像検査による正確な診断 と、保存療法から再生医療まで幅広い治療選択肢を用意しています。
- 超音波ガイド下の注射で安全かつ的確な治療
- 理学療法士によるリハビリとフォーム指導
- PRP療法など再生医療による先進的な治療
肘の痛みや違和感でお悩みの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。
テニス肘に関するよくある質問(Q&A)
テニス肘は自然に治りますか?
軽症のテニス肘であれば、数週間〜数ヶ月で自然に改善することもあります。
しかし、手首や肘を使い続ける生活習慣 があると慢性化しやすく、数ヶ月〜1年以上症状が続くケースも珍しくありません。
「放置すれば治るだろう」と思わず、早めの診察・リハビリ・生活指導 を受けることで、回復を早め再発予防にもつながります。
テニス肘に効果的なストレッチはありますか?
はい、ストレッチは再発予防にとても有効です。
代表的なのは 前腕伸筋群ストレッチ です。
- 片腕を前に伸ばして肘を伸ばす
- 反対の手で手首を下方向に軽く押し、前腕の外側が伸びるのを感じる
- 20〜30秒を1日数回繰り返す
ただし、痛みが強い時期はストレッチで悪化する場合もある ため、症状が落ち着いてから行うのが安全です。
テニス肘用のサポーターやエルボーバンドは有効ですか?
有効です。
エルボーバンド(カウンターフォースバンド)を肘より少し手首側に装着すると、腱付着部へのストレスを軽減できます。
ただし、サポーターはあくまで補助的な治療であり、根本改善にはリハビリや生活習慣の見直しが必要です。
テニス肘の注射治療は安全ですか?
当院では 超音波ガイド下で注射 を行うため、安全かつ正確に患部へ薬剤を届けられます。
- ステロイド注射:強い炎症や痛みに即効性がありますが、繰り返すと腱の脆弱化リスクがあるため回数は制限。
- ハイドロリリース:生理食塩水を注入して筋膜の癒着を改善。副作用が少なく安全性が高い。
- PRP療法:自分の血液を利用して腱の修復を促す再生医療。副作用リスクが少なく、アスリートにも選ばれています。
予防する方法はありますか?
予防のポイントは次の通りです。
- ストレッチ・筋トレ:前腕の筋肉を柔らかく、かつ強く保つ
- フォーム改善:テニスやゴルフの動作で負担を減らす
- 作業環境の見直し:デスクワーク時は肘や手首に無理がかからない姿勢を保つ
- 両手を使う習慣:買い物袋や鍋などは片手だけで持たず、両手で負担を分散する
テニスを続けても大丈夫ですか?
症状の程度によります。
軽度であればサポーターやフォーム改善を行いながら続けることも可能です。
しかし、強い痛みが出ているときは一時的に中止し、炎症を落ち着かせることが大切 です。
無理をしてプレーを続けると慢性化し、回復までに長期間を要することがあります。