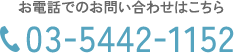腱鞘炎について

腱鞘炎(けんしょうえん)は、手指や手首を酷使することにより、筋肉の動きを支える「腱」と、それを包み滑らかな動きを助ける「腱鞘(けんしょう)」との間で摩擦が生じ、炎症が起きる状態です。
日常的な動作に深く関わる部位であるため、症状が悪化すると、痛みだけでなく動かしづらさや生活の質の低下にもつながります。
よくある腱鞘炎の種類
ばね指(弾発指)
指の付け根に痛みや腫れが起こり、曲げ伸ばしの際に引っかかるような感覚や「カクン」というばねのような現象が生じます。
悪化すると、指が途中で動かなくなる、痛くて伸ばせないといった症状が現れます。更年期の女性、育児中の方、手作業が多い方によくみられます。
ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)
手首の親指側にある腱が腱鞘との摩擦によって炎症を起こす病気です。
物をつかむ、赤ちゃんを抱っこする、スマホを操作するなどの動作で強い痛みが出ます。育児中の方に特に多く見られることから「抱っこ腱鞘炎」とも呼ばれます。
ばね指について
ばね指は、腱鞘炎の一種で、指を曲げた際に引っかかりを感じ、その後バネのように急に伸びる動きが特徴です。主に親指・中指・薬指に多く見られ、腱と腱鞘の間で炎症が起きることによって発症します。
放置すると、関節の柔軟性が低下し、スムーズな動きができなくなる「関節拘縮」へと進行する可能性があります。特に第2関節に拘縮が起きやすく、日常生活の動作に支障をきたす恐れがあります。
関節拘縮が進行すると回復が難しくなるため、指の引っかかりや違和感を覚えたら、できるだけ早めに当院へご相談ください。
ばね指の主な症状
- 指をまっすぐに伸ばしにくい
- 曲げ伸ばしの途中で引っかかりが生じ、その後バネのように勢いよく伸びる
- 関節の動きが滑らかでなく、動かしにくいと感じる
- 指を曲げるときに痛むことがある
ばね指の原因
 指を曲げ伸ばしするためには「腱」と呼ばれるヒモ状の組織が必要です。これらの腱は、靱帯性腱鞘(じんたいせいけんしょう)というトンネル状の構造の中を滑るように動きながら、指の関節を屈伸させています。
指を曲げ伸ばしするためには「腱」と呼ばれるヒモ状の組織が必要です。これらの腱は、靱帯性腱鞘(じんたいせいけんしょう)というトンネル状の構造の中を滑るように動きながら、指の関節を屈伸させています。
親指には腱が1本、その他の4本の指にはそれぞれ2本の腱が存在し、それぞれがこの腱鞘の中を行き来しています。
ところが、手や指を使いすぎると、腱と腱鞘の間で摩擦が生じて炎症が発生します。炎症が続くと、腱鞘が厚く硬くなり、腱の動きがスムーズでなくなってしまいます。その結果、腱が腱鞘の中で引っかかるようになり、バネのようにカクンと動く「ばね指」の症状が現れます。
このように、ばね指は以下のメカニズムで発症します:
手指の反復使用による摩擦 → 腱鞘の炎症と肥厚(腫れ・厚み) → 腱との隙間が狭くなり、動きが悪化 → 引っかかりやバネ現象が起きる
特に育児・家事・手作業・キーボード操作・楽器演奏・スポーツなど、同じ動作を繰り返す職業・趣味の方に多く見られます。
また、加齢やホルモンバランスの変化(更年期・妊娠中・産後)も発症に関与するとされており、40〜60代女性に多いのもこのためです。
早期に治療を行うことで炎症や腱の損傷を最小限に抑えることができます。引っかかり感や違和感を覚えたら、早めの受診が重要です。
ばね指の診断・治療
診断
ばね指は、問診と触診を中心に診断します。具体的には、指を曲げたときに引っかかりがあるか、音がするか、痛みのある部位を確認します。また、指を押したときの圧痛や腫れの有無、腱の動きの状態なども診察の重要なポイントです。
さらに必要に応じて、X線(レントゲン)検査や超音波(エコー)検査を行い、腱や腱鞘の状態を詳しく確認します。ばね指と似た症状を呈する他の疾患(例:関節リウマチ、感染性腱鞘炎など)との鑑別も重要なため、症状のある指だけでなく、他の指や手関節の状態も総合的に評価します。
特にリウマチや糖尿病などの持病がある方は複数の指に症状が出やすい傾向があるため、慎重な診察が必要です。
治療方針
ばね指の治療は、症状の程度に応じて以下のように段階的に行います。
保存療法(手術以外の治療)
- 安静・ストレッチ指導:指の使いすぎを避け、負担を軽減します。リハビリやストレッチにより、腱と腱鞘の動きを改善します。
- 薬物療法:消炎鎮痛薬(NSAIDs)の内服や湿布を使って炎症を抑えます。
- エコーガイド下注射:超音波で腱や腱鞘を確認しながら、ステロイド薬を正確に患部へ注入します。効果は高いですが、腱の脆弱化を防ぐために注射回数には制限があります。
手術療法
保存療法で十分な改善が見られない場合や、症状を繰り返すケース、強い拘縮があるケースでは、手術を検討します。
具体的には、局所麻酔下で1cmほど皮膚を切開し、肥厚した腱鞘を切開する「腱鞘切開術」を行います。術後はスムーズに腱が動くようになり、ほとんどの方が早期に日常生活へ復帰可能です。
ドケルバン病(ドケルバン腱鞘炎)について
 ドケルバン病(ドケルバン腱鞘炎)は、手首の親指側にある腱(短母指伸筋腱・長母指外転筋腱)と、その腱を包む腱鞘との間で炎症が生じる疾患です。
ドケルバン病(ドケルバン腱鞘炎)は、手首の親指側にある腱(短母指伸筋腱・長母指外転筋腱)と、その腱を包む腱鞘との間で炎症が生じる疾患です。
この腱と腱鞘の間の通り道(腱鞘トンネル)が狭くなることで、腱の滑りが悪くなり、痛みや腫れが起こります。特に親指を動かす・物を握る・持ち上げる・雑巾を絞るといった動作で症状が強くなります。
ドケルバン病の主な症状
- 手首の親指側に痛みや腫れ
- 親指を動かすとズキッとした痛みが出る
- 赤ちゃんを抱っこすると手首に激痛が走る
- ドアノブを回したり、瓶のふたを開けるのがつらい
- 朝方に特に痛みを感じることがある
ドケルバン病の原因
親指の腱と腱鞘の間に炎症が起こることで発症します
ドケルバン病は、親指を動かす2本の腱である
- 短母指伸筋腱(たんぼししんきんけん)
- 長母指外転筋腱(ちょうぼしがいてんきんけん)
と、これらの腱を包んでいる腱鞘(けんしょう)の間に生じる摩擦や炎症が原因です。
本来、腱は腱鞘というトンネルの中を滑らかに動くことで、スムーズな指の動きが可能になります。しかし、使いすぎや負荷がかかることでこの部分に炎症が起きると、腱の滑りが悪くなり、腱鞘内で動きが引っかかるようになります。
これにより、手首の親指側に
- ズキズキとした痛み
- 腫れや熱感
- 動かしにくさや可動域制限
などの症状が現れるのです。
主な要因としては以下が挙げられます:
- 手首や親指の使いすぎ(オーバーユース)
例:育児、介護、家事、調理、PC作業、スマホ操作など - 妊娠・出産期や更年期によるホルモンバランスの変化
特に女性に多い傾向があります - 手首の構造的問題(腱鞘が狭いなど)
- 加齢による腱や腱鞘の変性
- 関節リウマチや糖尿病などの基礎疾患
ドケルバン病の診断・治療
診断:問診・触診・画像検査を組み合わせて行います
ドケルバン病の診断では、まず問診で症状の経過や生活背景をお伺いします。その後、触診にて炎症の有無や痛みの場所を確認し、次のような誘発テストを行います。
フィンケルシュタインテスト
親指を握りこんだ状態で手首を小指側に倒し、親指側の手首に痛みが出るかを確認します。
さらに、当院では超音波検査(エコー)を活用し、炎症による腱や腱鞘の腫れ・むくみ・滑走障害を可視化します。
必要に応じてX線(レントゲン)検査も併用し、骨や関節に異常がないか確認します(※他の疾患との鑑別のため、画像検査は重要です)。
治療:症状の程度に応じて段階的に対応します
1. 保存療法(軽症例)
- 安静・装具療法:サポーターやテーピングを用いて手首を固定し、腱の動きを制限します。
- 消炎鎮痛薬・湿布:炎症を抑えるために外用薬や内服薬を使用します。
2. 注射治療(中等症〜反復例)
痛みや腫れが強い場合、もしくは保存療法で効果が不十分な場合には、エコーガイド下で腱鞘内にステロイドや局所麻酔薬を注入します。
炎症を直接抑えることで、多くの患者様で1〜2回の注射で改善が見込めます。
※ただし、注射の効果が一時的であったり、再発を繰り返す場合もあるため、適切な時期に次のステップに進む判断が必要です。
3. 手術療法(重症例・再発例)
症状が強く、繰り返す痛みや可動制限に悩まされる場合は、腱鞘切開術を行うことがあります。これは狭くなった腱鞘を切開して腱の通り道を広げ、腱の滑走を回復させる手術です。
日帰りでの対応が可能で、術後の回復も比較的早いのが特徴です。
腱鞘炎の発症リスクが高い方の特徴
腱鞘炎になりやすい方の特徴
腱鞘炎は、手や指、手首を繰り返し使うことで起こる炎症性疾患です。そのため、特定の職業や生活習慣、ホルモンバランスの変化などによって、発症リスクが高まることが知られています。
日常的に手を酷使する方
腱や腱鞘に繰り返し負荷がかかることで炎症が起こりやすく、以下のような動作や趣味・仕事に従事されている方は注意が必要です。
- スマートフォンやパソコンの長時間使用
- 裁縫・編み物・陶芸・木工などの手作業
- ギター・ピアノなどの楽器演奏
- テニスやバドミントンなどラケット競技
- 絵画・書道・デザイン作業
これらの動作は一見軽そうに見えても、手指の屈伸運動を反復的に行うため、腱鞘への負担が蓄積しやすく、知らず知らずのうちに炎症へとつながる場合があります。
ホルモンバランスの変化がある女性
女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの減少は、腱や靭帯の柔軟性の低下を招き、腱鞘炎のリスクを高めるとされています。
特に以下の時期は注意が必要です。
- 妊娠・出産後の育児期
- 更年期(40代後半〜50代以降
これらの時期に加え、抱っこやおむつ替えなど、手首に負担がかかる動作が多い子育て世代の女性は、ドケルバン病やばね指などを発症することが少なくありません。
持病のある方(関節リウマチ・糖尿病など)
- 関節リウマチ:全身の関節や腱に炎症を引き起こす自己免疫疾患で、腱鞘炎を合併しやすい。
- 糖尿病:血糖コントロール不良により腱のコラーゲンが変性しやすく、ばね指の発症頻度が高いとされています。
これらの基礎疾患をお持ちの方は、早期発見・早期治療が重要です。片手だけでなく複数の指に症状が出るケースも多く見られます
腱鞘炎の予防
作業環境を見直す
作業環境を見直して手首への負担を軽減
- 長時間のデスクワークや繰り返しの手作業を行う方は、作業環境の最適化が重要です。
- パソコン作業では、机や椅子の高さ、モニター・キーボードの角度を自分に合うように調整しましょう。
- アームレストの活用や、キーボード・マウス操作の際に手首が宙に浮かない工夫も有効です。
パソコン以外でも、作業台の高さ・道具の配置などを工夫することで、手首の過剰な伸展や屈曲を防ぐことができます。
身体に負担の少ないフォームを身につける
日常動作やスポーツでの誤ったフォームや反復動作は、腱鞘炎の原因となることがあります。
筋肉に無理な力をかけない「正しい動作」を身につけることで、負担を軽減できます。
持病を管理して炎症リスクを減らす
以下のような持病をお持ちの方は、腱や腱鞘に炎症が起こりやすく、腱鞘炎を合併しやすい傾向があります。
- 関節リウマチ
- 糖尿病
- 甲状腺機能異常
こうした基礎疾患の治療継続・良好な管理は、腱鞘炎の予防にも直結します。
腱鞘炎を発症した場合の対応
腱鞘炎を発症した場合は、まず手指や手首の使用をできるだけ控え、患部をしっかり休ませることが回復への第一歩となります。痛みのある部位を動かさないように、テーピングやサポーターで固定することも効果的です。
炎症による熱感や腫れがある場合は、氷嚢などを使って冷却することで症状の緩和が期待できます。ただし、冷やしすぎには注意が必要です。1回の冷却時間は20分程度を目安とし、それでも熱感や腫れが残っている場合は、2時間ほどあけてから再度20分ほど冷やしてください。
ドケルバン病に関するよくある質問(Q&A)
ドケルバン病とはどんな病気ですか?
ドケルバン病は、親指の付け根から手首にかけて通っている腱(短母指伸筋腱・長母指外転筋腱)が、通り道である腱鞘でこすれて炎症を起こす「狭窄性腱鞘炎」です。
親指を動かすたびに腱と腱鞘が摩擦を起こし、親指の付け根の痛みや腫れ、動かしづらさ が出るのが特徴です。
特に 妊娠・出産期の女性、育児中の方、更年期の女性 に多く見られます。
どうして女性に多いのですか?
ホルモンバランスの変化が関係しています。
妊娠や授乳期、更年期はホルモンの影響で腱や腱鞘がむくみやすくなり、炎症が起こりやすくなります。
また、育児中は赤ちゃんを抱っこしたり授乳姿勢をとったりすることで 親指と手首に負担が集中 するため、ドケルバン病が発症しやすくなります。
自分でチェックする方法はありますか?
有名なセルフチェックとして フィンケルシュタインテスト があります。
- 親指を中に入れて拳を握る
- そのまま手首を小指側に倒す
この動作で親指の付け根から手首にかけて強い痛みが出た場合は、ドケルバン病の可能性があります。
サポーターやテーピングは効果がありますか?
はい、効果的です。
親指や手首を固定して安静にすることで腱の摩擦が減り、炎症が落ち着きやすくなります。
市販の親指付き手首サポーターは日常生活のサポートに有効ですが、サイズや形が合わないと逆効果になることもありますので、医師や理学療法士の指導のもとで使用するのが安心です。
注射で治りますか?
炎症や痛みが強い場合には、ステロイド注射を行うことがあります。
超音波ガイド下で正確に腱鞘内へ注入することで、炎症を和らげ、数日で症状が軽減する方も多いです。
ただし、効果は一時的なこともあり、再発する可能性もあります。
手術が必要になることはありますか?
保存療法(安静・装具・薬・注射)で改善しない場合、腱鞘を切開して腱の通り道を広げる手術が検討されます。
手術は局所麻酔で行われ、比較的短時間で終了します。再発は少なく、予後は良好です。
予防する方法はありますか?
手首や親指に負担をかけすぎないことが大切です。
- 長時間のスマホ操作を控える
- 赤ちゃんの抱き方を工夫する(手首だけに負担をかけない)
- 家事やパソコン作業の合間にストレッチを取り入れる
- 親指や手首を冷やさない
無理を続けると慢性化するため、早めの受診・治療が予防につながります。