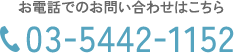低身長とは
子どもの身長が一定の基準を下回っている、または1年間に伸びる身長(成長率)が著しく低い場合、「低身長」と診断されることがあります。
医学的には、
- 同じ年齢・性別の平均身長と比べて標準偏差(SD)で-2SD未満の場合
- 年間の成長率が同性・同年齢の子どもの平均値の-1.5SD以下で、2年以上続く場合

低身長は多くの場合は身体に異常がないですが、単に「背が低い」だけではなく、成長ホルモンの分泌異常、遺伝的要因、慢性的な疾患、栄養状態など、背景にさまざまな要因が隠れている可能性もあります。
また、見た目の身長だけでなく、成長のスピード(成長曲線の推移)が遅れていることも重要なサインです。例えば、同級生と比べて急に差が広がってきた、思春期が遅れているといった場合は専門的な評価が必要になります。
成長に関して気になることがある場合、早めに医療機関で相談することが大切です。当院では、小児の成長ホルモン治療に携わってきた経験をもとに、適切な治療を行っております。
低身長の原因
成長は「栄養」「ホルモン」「骨の発育」「精神的な安定」といった複数の要素が組み合わさって進みます。どれかひとつでも不調があると、身長の伸びが妨げられることがあります。
さらに、出生時から小柄でその後の発育が追いつかないケースや、一時的に身長が伸びても思春期が早く訪れることで成長が止まってしまうケースもあり、注意が必要です。
したがって、低身長が「体質的な範囲内」なのか「治療を要する病的なもの」なのかを正しく見極めることが大切です。成長期を逃さずに適切な治療を行うことで、将来の最終身長を改善できる可能性もあります。
当院では、成長曲線やホルモン検査、画像検査などを組み合わせて、お子様の成長を多角的に評価いたします。
遺伝的な要因
身長は親の体格からの影響を大きく受けます。両親の身長が低めの場合、お子様も「体質性低身長」として身長が低い傾向にあります。これは病気ではなく治療を必要としないことも多いですが、まれに他の疾患が隠れている場合もあるため、気になるときは一度医師に相談することが大切です。
栄養不足
成長に必要な栄養素(タンパク質、カルシウム、亜鉛、ビタミンなど)が不足すると、骨や筋肉の発育が十分に行われず、身長の伸びが妨げられることがあります。偏食や極端な食事制限は注意が必要です。
ストレスや生活環境
精神的なストレスや生活リズムの乱れは、成長ホルモンの分泌を低下させることがあります。学校生活の環境変化や心理的ストレスが影響する場合もあります。
内分泌疾患
成長ホルモンの分泌不全や甲状腺ホルモンの不足、性ホルモンの異常など、ホルモン分泌に関わる疾患が低身長の原因となることがあります。こうした場合は専門的な検査と治療が必要です。
骨や染色体の異常
骨や軟骨の発育に障害がある場合、身長の伸びが抑えられます。また、ターナー症候群などの染色体異常でも低身長が見られます。体格に特徴的なバランスの違いがある場合には注意が必要です。
出生時からの発育不全(SGA児)
生まれたときから小さく、その後も十分に身長が追いつかないケースがあります。適切な時期に治療を行うことで、成長を促進できる場合があります。
思春期早発症
一時的に成長が早く進んだように見えても、骨の成熟が早まることでその後の成長が早期に止まり、結果的に最終身長が低くなる場合があります。
日頃から身長や体重を「成長曲線」に沿って記録し、平均的な成長と比べて著しい差がないかを確認することが大切です。
当院では、母子手帳や学校健診のデータをもとに成長曲線を作成し、詳しく評価いたします。
「背が低いのではないか」「成長が遅れているのでは」と心配なときは、お気軽にご相談ください。
小児低身長治療
成長ホルモン治療とは
この治療は、骨の成長が活発な時期に行う必要があるため、気になる症状がある場合はできるだけ早めにご相談ください。
また、必要に応じて骨の成長スピードを調整するための内服薬や注射、栄養補助も併用することがあります。
成長ホルモンを用いた小児の低身長治療について
保険適用
お子様の身長が「−2SD以下」、かつ成長ホルモン分泌不全などの医学的な条件を満たしていれば、保険適用で治療を受けることが可能です(詳細は診療ガイドラインに基づき判断されます)。
自費診療
一方で、「−2SD以上」ではあるものの、将来的に低身長となる可能性が高いと考えられるケースもあります。例えば、家族性低身長やSGA(子宮内発育不全児)などに該当し、骨端線が閉じていないお子様であれば、成長ホルモンによる自費治療の選択肢があります。
「生活習慣に気をつけて、運動や睡眠、食事にも配慮しているのに、思うように背が伸びない」といったお悩みをお持ちの保護者の方は、一度ご相談ください。精密検査を実施し、成長ホルモン補充による治療が適応となる場合には、厚生労働省や米国FDAの基準に準じたガイドラインに沿って、自費での治療を行うことができます。
治療の対象年齢
概ね6歳から思春期(男子で14~15歳前後、女子で12~13歳前後)までが適応ですが、成長スピードや骨の成熟度には個人差があります。
※骨端線(成長軟骨)が閉じると治療は終了となります。
治療の効果が期待できる時期
3歳から思春期までの成長には「栄養+成長ホルモン」が重要ですが、思春期に入ると「性ホルモン」の影響が強くなり、成長ホルモンの役割が次第に小さくなります。そのため、6歳~11歳頃に治療を始めるのが最も効果的と言われています。
低身長治療の流れ
1初診
はじめに問診票を記入頂きます。以下のものをご用意ください。
お持ち頂くもの
- 母子手帳
- 幼児期から小中学生までの身長記録(成長過程が分かる資料)
 これらをもとに、当院で成長曲線を作成していただきます。
これらをもとに、当院で成長曲線を作成していただきます。
食生活、生活環境、家族の身長、病歴なども含めて詳しくお伺いします。
初診時には血液検査やX線検査も実施します。
初診費用※自費の場合
| 相談のみ | 5,500円(税込) |
|---|---|
| 問診+検査(レントゲン+採血) | 27,500円(税込) |
22回目(初診から約1週間後)
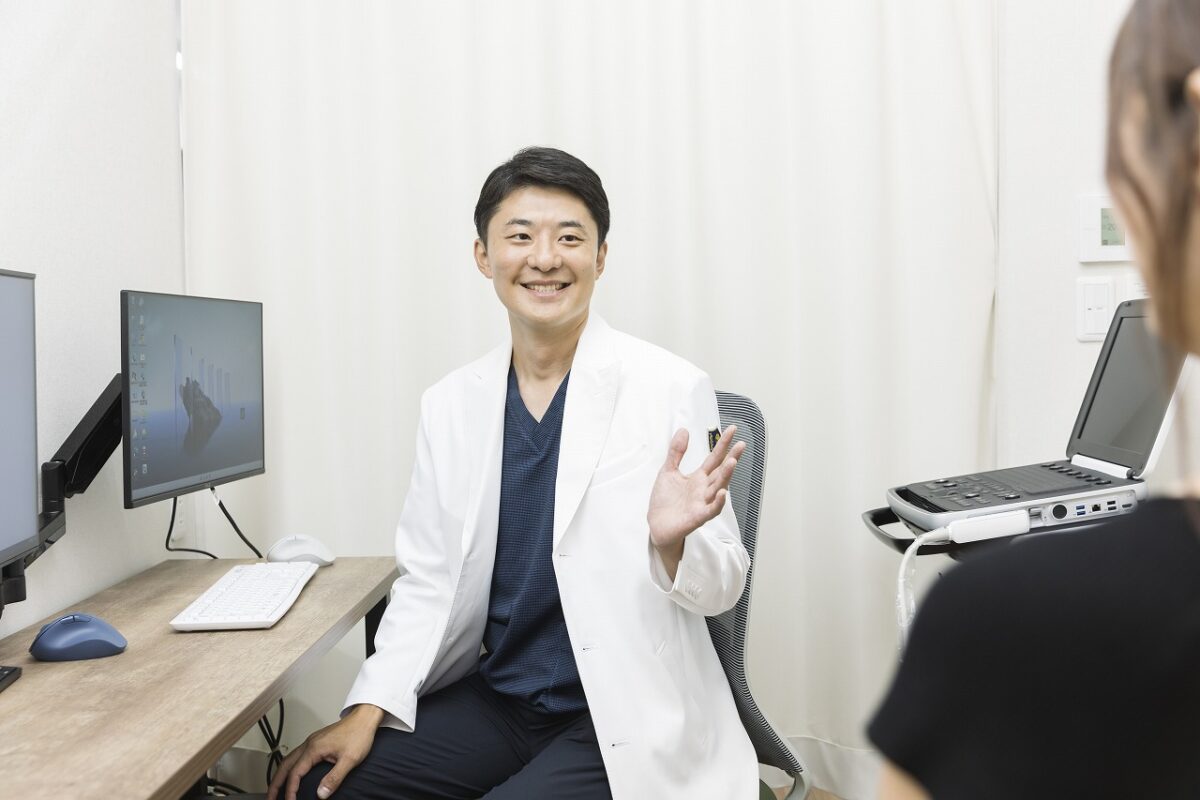 検査結果をもとに医師が治療の適応可否を判断します。
検査結果をもとに医師が治療の適応可否を判断します。
必要であれば成長ホルモンの分泌不可試験の日程調整を行います
お薬代の目安
成長ホルモン1アンプル:60,000円(税込)
33回目(治療開始から約1ヶ月後)
診察・検査・薬剤の再処方を行います。
効果や副作用を確認しながら継続します。定期的なフォローアップが必要です。
※成長ホルモン治療は体質によって反応に差があり、高い効果を実感されるお子さんもいれば、効果が限定的なケースもあります。個人差があることをご理解ください。
※治療が安定すればお薬の長期処方が可能ですが、年に数回は必ず診察と検査を行います。
※以下の方は治療対象外となります。
糖尿病・悪性腫瘍のある方、妊娠中の方、プラダーウィリー症候群の方、その他特殊疾患など
※治療はご自宅での自己注射となるため、保護者の管理ができるご家庭のお子様に限ります。医師の指示に従い、継続的な通院が可能な方が対象です。
※本治療は上記の一部のお子さんを除き、自費診療となります。
主な副作用
成長ホルモン治療により、以下の副作用が見られることがあります。
- 糖尿病や悪性腫瘍の増殖
- 腎臓・心臓への負担
- 脊椎側弯症の進行
- 頭痛や痙攣など
これらのリスクがあるため、治療中は医師の指導のもと定期的な検査と経過観察が必要です。
費用(自費の場合)
初診
| 相談のみ | 5,500円(税込) |
|---|---|
| 問診+検査(レントゲン+採血) | 27,500円(税込) |
再診
| 診察のみ | 1,650円(税込) |
|---|---|
| 診察+採血 | 14,300円(税込) |
| 診察+採血、レントゲン | 16,500円(税込) |
| 成長ホルモン 1本 | 60,000円(税込) |
|---|---|
| 亜鉛 30錠 | 12,000円(税込) |
| プリモボラン 30錠 | 4,950円(税込) |
| リュープリン1.88 | 19,800円(税込) |
| リュープリン3.75 | 24,200円(税込) |
低身長に関するよくある質問
治療はいつ始めるのが良いですか?
成長ホルモンの影響を最も受けやすいのは 5歳~12歳頃 とされています。
この時期に治療を開始することで、成長率が高まりやすく、将来的な身長改善につながります。
もちろん、それ以降の年齢でも治療は可能ですが、骨端線の状態や思春期の進行度には個人差があります。
適切なタイミングを逃さないためにも、早めの受診・相談をお勧めします。
サプリメントで本当に身長は伸びますか?
現在の医学的な知見では、直接的に身長を伸ばす効果が証明されたサプリメントは存在しません。
日本小児内分泌学会の公式サイトにもその旨が明記されています。
サプリメントに費用をかけるよりも、栄養バランスの良い食事・規則正しい生活習慣を整えることが大切です。
気になる場合は、医師にご相談ください。
身長を伸ばすために必要な食事は何ですか?
成長期には以下の栄養素が特に重要です。
- タンパク質(肉・魚・卵・大豆製品)
- カルシウム(牛乳・乳製品・小魚・緑黄色野菜)
- 亜鉛(牡蠣・レバー・赤身肉・ナッツ類)
まずは「食べることを楽しむ」ことが大切です。お子様の好みに合わせつつ、少しずつ食材の幅を広げていきましょう。
身長を伸ばすために良い運動はありますか?
特定の運動だけが有効というわけではありません。
継続的に体を動かす習慣を持つことが重要です。
- 運動を継続すると基礎代謝や心肺機能が向上
- 睡眠の質が改善される
- その結果、成長ホルモンの分泌を助ける効果が期待できます
遺伝の影響はどのくらいありますか?
身長には遺伝的要因が大きく関与しています。
両親の身長から将来の予測身長を算出する「両親平均身長(MPH:Mid-Parental Height)」が参考になりますが、必ずしも一致するわけではありません。
栄養状態やホルモンの分泌、病気の有無、生活習慣など環境要因も大きく影響します。
睡眠は身長の伸びに関係しますか?
はい、大きく関係します。
成長ホルモンは主に「深い睡眠(ノンレム睡眠)」の間に分泌されます。
十分な睡眠時間と規則正しい生活リズムを確保することで、成長を助けることができます。
成長ホルモン治療は痛みがありますか?
治療は細い針を使った自己注射で行います。
痛みはインフルエンザの予防接種よりも弱い程度で、多くのお子様が慣れて継続できています。
ご家庭での自己注射に不安がある場合は、医師・看護師が丁寧にサポートしますのでご安心ください。