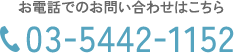ロコモティブシンドロームについて
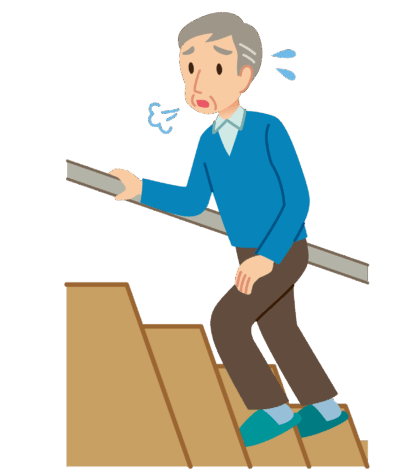 ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)とは、加齢や運動不足、筋力低下、運動器疾患などにより、立つ・歩くといった基本的な移動能力が低下した状態を指します。日本語では「運動器症候群」と呼ばれ、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)や認知症と並んで、健康寿命を縮める3大要因のひとつに挙げられています。
ロコモティブシンドローム(locomotive syndrome)とは、加齢や運動不足、筋力低下、運動器疾患などにより、立つ・歩くといった基本的な移動能力が低下した状態を指します。日本語では「運動器症候群」と呼ばれ、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)や認知症と並んで、健康寿命を縮める3大要因のひとつに挙げられています。
筋肉・骨・関節・軟骨・椎間板など、身体の動きを支える「運動器」のいずれかに異常が起こると、移動機能が徐々に低下し、歩行困難や転倒・骨折のリスク、将来的な寝たきりや要介護状態のリスクが高まります。
ロコモティブシンドロームの特徴的な点は、すでに介助が必要な状態だけでなく、「今後、要介護になる可能性が高い状態」も含めて対象となることです。つまり、早期の自覚と予防が非常に重要なのです。
ロコモを引き起こす主な要因
加齢による筋力・バランス能力の低下(サルコペニア)
年齢とともに筋肉量が減少し、筋力やバランス能力が低下します。
これにより、転びやすくなったり、日常生活の動作が億劫になる「運動機能の低下」が進行します。
運動器の疾患や障害
- 変形性膝関節症
- 変形性脊椎症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症や圧迫骨折
など、運動器そのものの病気や障害もロコモの主因となります。
関節の変形や痛みによって活動量が減り、さらに筋力が衰えるという悪循環に陥ります。
運動不足や生活習慣の影響
デスクワーク中心の生活、歩行機会の減少、体重増加なども、筋力・柔軟性・骨密度の低下につながり、ロコモを引き起こしやすくなります。
発症年齢と背景
ロコモは高齢者だけの問題ではありません。
40代頃からすでに兆候が見られることもあり、筋力低下や関節痛などを「年齢のせい」として放置すると、気づかぬうちに進行しているケースも少なくありません。 「最近つまずきやすい」「歩くスピードが遅くなった」「階段の昇降がつらい」と感じる方は、すでにロコモの初期段階に差しかかっている可能性があります。
健康寿命とは?
健康寿命とは、「介護を受けることなく、自立した生活を送れる期間」のことを指します。
単なる平均寿命とは異なり、「健康で活動的に暮らせる年数」のことを意味します。日本人の平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年の差があるとされており、これは「人生の最期の約10年間は何らかの介助が必要になる可能性がある」ことを示唆しています。
ロコモと健康寿命の深い関係
この健康寿命を脅かす大きな原因の一つが、「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」です。
加齢や運動不足などにより、筋肉・骨・関節など運動器の機能が低下すると、立つ・歩くといった基本的な動作が難しくなり、転倒や骨折、寝たきりなどのリスクが高まります。 実際に、要介護となる主な原因の上位には、関節疾患や骨折・転倒、脊椎疾患などの運動器障害が含まれており、ロコモは健康寿命を縮める大きな要因とされています。
ロコモ対策が「自分の未来」と「家族」を守る
運動器の障害は、ご本人のQOL(生活の質)を大きく下げるだけでなく、ご家族や周囲の方にも精神的・身体的・経済的な負担を与える可能性があります。 健康で自立した生活をできる限り長く保つためには、早期からロコモを予防し、運動器の健康を維持することが非常に重要です。
「健康に長生きしたい」「寝たきりになりたくない」「家族に迷惑をかけたくない」
――そんな思いをお持ちの方は、40代・50代からのロコモ対策がカギとなります。
ロコモティブシンドロームのセルフチェック
(ロコチェック)
「最近、つまずきやすくなった」「以前より動作が億劫に感じる」といったちょっとした身体の変化は、ロコモティブシンドローム(ロコモ)のサインかもしれません。
ロコモの兆候は、日常生活の中に現れます ロコモは、運動器の機能低下によって要支援・要介護のリスクが高まる状態を指しますが、発症の初期段階では「年齢のせいかな」と見過ごされがちです。早期に気づき、対策を講じることが、健康寿命を延ばすための第一歩となります。
そのために活用したいのが、日本整形外科学会が提唱する「ロコチェック」です。
ロコチェックの7項目
以下の7つのチェック項目のうち、1つでも当てはまる場合は、ロコモの可能性があります。
予防・改善のために、整形外科での評価や運動習慣の見直しをおすすめします。
- 室内でつまずいたり、滑ったりする
- 靴下を片足立ちで履けない
- 階段を上がるときに手すりが必要
- 横断歩道を青信号の間に渡りきれない
- 15分以上続けて歩くのが難しい
- 牛乳パック2本(約2kg)の買い物袋を持って帰るのがつらい
- 布団の上げ下ろしや掃除機がけなどの家事がしんどい
ロコチェックは無料で簡単に実施できます
このチェックは自宅で簡単に行うことができ、特別な道具や測定器は必要ありません。
まずは気軽に試してみて、自分の身体状態を客観的に把握することが大切です。
より詳しい評価をご希望の方には、当院にて運動機能の検査や、理学療法士による指導も承っております。
気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。
予防には「ロコトレ」が効果的です
ロコモティブシンドローム(ロコモ)の進行を防ぎ、健康寿命を延ばすためには、日々の運動習慣が非常に重要です。
特に「ロコチェック」で1項目でも該当した方は、今後の要介護リスクを減らすためにも、積極的な予防対策が求められます。
ロコモーショントレーニング(ロコトレ)とは?
「ロコトレ」とは、筋力やバランス能力を鍛えることで、立つ・歩くといった基本動作の維持・改善を目指す運動プログラムです。
日本整形外科学会も推奨しており、以下のような運動が中心となります。
- 片脚立ち:左右各1分ずつ行うことで、バランス機能や下肢筋力を向上させます
- スクワット:太ももやお尻、体幹の筋肉を効果的に鍛えられる基本的な動作です
- その他のトレーニング:筋力トレーニングマシンを活用した下肢トレーニングや歩行訓練など
無理のない範囲で、継続的に実施することが効果的です。
医学的なサポートのもとで、安全にロコモ対策を
ロコモの背景には、変形性関節症、骨粗鬆症、脊椎の変形などの整形外科的疾患が隠れていることも少なくありません。
そのため、明らかな痛みや違和感がある方、既に整形外科的な診断を受けている方は、自己判断ではなくまずは医師の診察を受けてください。
当院では、ロコモが疑われる方に対し、症状や運動機能に応じたリハビリテーションや個別トレーニングプログラムの提案を行っております。
必要に応じて理学療法士がマンツーマンで指導を行い、転倒予防や機能改善を丁寧にサポートします。
当院で行うロコモティブシンドローム対策・リハビリ内容
ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、放置してしまうと将来的に歩行困難や寝たきり、要介護のリスクが高まるため、早期の対策と継続的なケアが重要です。当院では、整形外科専門医と理学療法士が連携し、一人ひとりの状態に合わせたロコモ対策・リハビリテーションを提供しています。
1. 医師による評価と診断
 まずは、整形外科専門医が詳細な問診と身体診察を行います。
まずは、整形外科専門医が詳細な問診と身体診察を行います。
必要に応じてX線やMRIなどの画像検査を行い、運動器疾患の有無(変形性関節症、骨粗鬆症、椎間板障害など)を把握します。疾患がある場合にはその治療を優先し、並行して運動指導・生活習慣の改善にも取り組みます。
2. 理学療法士による個別リハビリテーション
当院では、理学療法士によるマンツーマンの運動療法を行っております。
ロコモの進行度や身体機能に応じて、以下のようなプログラムを個別に組み立てていきます。
- バランストレーニング:転倒予防や歩行安定性の向上
- 筋力トレーニング:太もも・お尻・体幹の筋力を高め、日常動作を楽にします
- ストレッチ指導:股関節・膝関節・足関節の可動域を改善
- 姿勢や歩行の矯正:正しい姿勢や重心のとり方を指導し、腰や膝への負担を軽減
- 生活指導:自宅でできる運動(ロコトレ)や姿勢改善法をわかりやすく説明
3. 継続的な評価とサポート
ロコモは一時的なリハビリで解消するものではなく、継続的な取り組みが必要です。
当院では定期的に機能評価を行い、進捗に応じてリハビリ内容の見直しや新たな目標の設定を行っています。
また、必要に応じて、家庭で実施できるホームプログラム(運動メニュー)を作成し、自立した生活の維持・向上を支援します。
4. 当院のロコモ対策はこのような方におすすめです
- 歩くとすぐ疲れる、転びそうになる
- 最近、膝や股関節に痛みが出てきた
- 骨粗鬆症の診断を受けたことがある
- 将来、寝たきりや介護が不安
- 健康寿命を伸ばしたい、介護を予防したい
よくあるご質問(FAQ)
ロコモティブシンドロームとサルコペニアはどう違うのですか?
ロコモは「運動器の障害により移動機能が低下した状態」を指す概念で、筋肉だけでなく骨、関節、椎間板なども含まれる広い範囲の障害が対象です。一方でサルコペニアは“筋肉量や筋力の低下”に特化した状態を指します。つまり、サルコペニアはロコモの一因であると理解されるとよいでしょう。
何歳くらいからロコモを意識すべきですか?
ロコモは早ければ40代から兆候が出始めることもあります。明らかな症状がなくても、「最近つまずきやすい」「立ち上がるのがつらい」と感じる方は、予備群の可能性があります。50代・60代では本格的に進行するケースが増えるため、できるだけ早期からの予防が重要です。
ロコチェックで1つでも当てはまったら病院に行くべきですか?
はい、1項目でも当てはまれば、ロコモの予備群とされており、整形外科的な評価を受けることが望ましいとされています。特に高齢者の方や既に関節や骨に疾患のある方は、状態の悪化を防ぐためにも早期受診がおすすめです。
ロコトレは自宅でもできますか?
はい、基本的なロコトレ(片脚立ちやスクワットなど)は、自宅でも安全に行える内容となっています。ただし、効果的に行うには正しいフォームや回数、頻度などの指導が必要です。当院では、理学療法士が患者様の状態に応じて、自宅でできる運動メニューもご提案しております。
ロコモは完全に治りますか?
ロコモ自体は病名ではなく「状態・概念」なので、“治す”というよりは「進行を防ぎ、機能を維持・改善する」ことが目標となります。早期からの対策によって、日常生活に支障のないレベルまで改善することは十分可能です。
痛みがある場合でもロコトレはしてよいですか?
痛みが強い場合にはまず原因となっている疾患(例:変形性膝関節症、骨粗鬆症など)の治療が優先されます。そのうえで、症状の程度に応じてリハビリメニューを調整しますので、無理に自己流で続けるのは避け、医師や理学療法士にご相談ください。
リハビリはどれくらいの頻度で通えばよいですか?
症状の程度やご本人の目標によって異なりますが、週1~2回の通院が基本です。必要に応じて、間の期間に自宅で行うトレーニングメニューを併用していただくことで、より効果的な改善が期待できます。