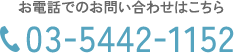痛風について
 痛風(つうふう)は、血液中の尿酸が過剰になることで起こる疾患です。
痛風(つうふう)は、血液中の尿酸が過剰になることで起こる疾患です。
医学的には「高尿酸血症に起因する急性関節炎」と定義されており、特に男性に多く、中年以降での発症が目立ちます。
高尿酸血症と結晶化
尿酸は、体内のプリン体という物質が分解されてできる老廃物の一種です。
通常は腎臓から尿として排出されますが、食生活の乱れや飲酒、肥満、ストレス、遺伝的体質などが影響して、尿酸値が慢性的に高くなると、血液中の尿酸が飽和状態となり、針のような尿酸結晶が関節内に析出します。
痛風発作とは
尿酸の結晶が関節内に沈着すると、免疫細胞がこれを異物と認識し、激しい炎症反応を起こします。
これが「痛風発作」です。典型的には、以下のような特徴があります。
- 発症は突然で、夜間や明け方に多い
- 足の親指の付け根(母趾のMTP関節)に強い痛み・腫れ・発赤が出現
- 歩行困難なほどの激痛
- 数日から1週間ほどで軽快することもあるが、再発を繰り返す
痛風の好発部位
- 足の親指の関節(第1中足趾節関節)
- 足首
- 膝
- くるぶし
- 肘 など
※左右対称でなく、片側の関節に急性発作として起こることが多いです。
放置すると起こる合併症
高尿酸血症や痛風を放置すると、次のような合併症リスクが高まります。
- 腎障害(痛風腎):尿酸の結晶が腎臓にも沈着し、腎機能が低下
- 尿路結石:尿酸が尿中に析出し、結石の原因に
- 動脈硬化・高血圧・心疾患・脳血管障害:高尿酸状態が血管機能に悪影響
早期受診のすすめ
健康診断などで「尿酸値が7.0mg/dL以上」と指摘された方は、高尿酸血症とされ、発作の有無にかかわらず注意が必要です。
痛みがある場合はもちろんですが、無症状でも放置せず、予防的治療や生活改善を行うことが将来的な関節炎や腎障害の予防につながります。
痛風の原因
痛風の原因|プリン体と生活習慣の関係
痛風は、体内の尿酸値が高くなること(高尿酸血症)によって引き起こされます。
尿酸は、プリン体と呼ばれる物質が体内で分解される際に作られる老廃物の一種で、通常は尿と一緒に排出されます。
しかし、尿酸が過剰に産生されたり、腎臓からの排泄が不十分になったりすると、血液中に尿酸が蓄積しやすくなります。
プリン体の摂りすぎが引き金に
特に、プリン体を多く含む食品(例:レバー、白子、アンコウの肝、日本酒、ビールなど)を頻繁に摂取する食生活は、尿酸値の上昇に直結します。また、脂質や糖質が過剰な食事は内臓脂肪の蓄積を招き、インスリン抵抗性や腎機能の低下を引き起こすことがあり、結果として尿酸の排泄機能も弱まってしまいます。
生活習慣も痛風リスクに
痛風の発症には、食生活だけでなく、アルコールの過剰摂取、運動不足、肥満、ストレス、脱水、遺伝的体質など、さまざまな生活習慣が関係しています。たとえば、アルコールは体内で尿酸の排泄を妨げる作用があるため、飲酒量が多い方は要注意です。
痛風を防ぐには?まずは生活改善から
痛風は、長年の生活習慣の積み重ねによって発症する「生活習慣病」の一つです。
したがって、バランスの取れた食事、適度な運動、水分摂取の習慣、節酒など、日々の生活の見直しが予防の第一歩です。健康診断で尿酸値の高さを指摘された場合は、発作が起きていない段階でも早めに対策を講じることが大切です。
痛風になりやすい方の特徴
生活習慣・体質から見るリスク
痛風は、体質だけでなく日々の生活習慣の影響を大きく受ける病気です。次のような傾向がある方は、痛風の発症リスクが高いとされています。
当てはまる項目が多い方は、早めの生活習慣の見直しと尿酸値の管理を心がけましょう。
1.食生活に関する要因
- プリン体を多く含む食品をよく食べる
肉類(特に内臓系)、レバー、魚卵(いくら・たらこ)、エビ、カツオ、マグロなど。 - アルコール、特にビールをよく飲む
ビールにはプリン体が多く含まれており、尿酸値を上昇させる原因になります。 - 甘いジュースや清涼飲料水を日常的に飲んでいる
果糖の過剰摂取は、尿酸の合成を促進します。
2.体質・性別・年齢による要因
- 30歳を超えた男性
痛風患者の多くは中年以降の男性に多く見られます。 - 家族に痛風の既往がある
痛風は遺伝的な体質も影響します。
3.ライフスタイル・運動習慣による要因
- 強度の高い運動を日常的に行っている
筋肉の代謝によって尿酸が産生されやすくなります。 - 水分補給が不十分
尿酸の排泄が低下し、体内に蓄積されやすくなります。 - 内臓脂肪が多い(肥満気味)
肥満は尿酸の排出を妨げる要因となり、生活習慣病全般のリスクを高めます。 - ストレスが多い・溜め込みやすい性格
精神的ストレスは体内の代謝を乱し、発作の引き金となることがあります。
早期の予防と生活改善が重要です
痛風は「贅沢病」と言われることもありますが、現代では誰でも発症しうる身近な疾患です。
特に上記のような傾向がある方は、健康診断での尿酸値チェックや、医療機関での相談をおすすめします。
食生活の見直し、水分摂取の意識、適切な運動と休養を心がけることで、痛風のリスクは大きく減らすことができます。
痛風の治療
生活習慣の改善から薬物療法まで
痛風の治療においては、「尿酸値を下げること」が最も重要な目標となります。
これは、痛みの原因である尿酸の結晶が体内に蓄積されないようにし、発作の再発を防ぐためです。
発作が起きていないときでも、治療を継続することが何よりも大切です。
1.まずは生活習慣の見直しから
- 治療の第一歩は、日々の食生活や生活習慣の改善です。
- プリン体を多く含む食品の摂取を控える
肉類や魚卵、内臓系の食材、アルコール(特にビール)などを減らす工夫が必要です。 - バランスの取れた食事を心がける
野菜や海藻類など、アルカリ性食品を適度に摂取し、体内の尿酸を中和する助けになります。 - 水分をしっかり摂る
尿量を増やすことで、尿酸の排出が促されます。目安として、1日2リットル以上の水分摂取が推奨されます(※腎疾患のある方は主治医にご相談ください)。 - 肥満の改善・運動習慣の見直し
急激な減量や激しい運動は発作の引き金となるため、適度な運動を継続することが効果的です。
2.尿酸値が下がらない場合は薬物治療へ
生活改善だけでは尿酸値がコントロールできない場合、内服薬による治療(薬物療法)を開始します。
- 尿酸の生成を抑える薬(例:アロプリノール)
- 尿酸の排泄を促進する薬(例:ベンズブロマロン、プロベネシド)
- 発作時の炎症を抑える薬(NSAIDsやステロイド)
※初期の薬物治療では、尿酸値の急激な変動により痛風発作が誘発されることもあるため、注意が必要です。医師の指示に従い、段階的に治療を行っていきます。
3.治療は「発作がない時期」こそ重要
痛風は、痛みがある時だけ治療すればよい病気ではありません。
発作が落ち着いていても、尿酸の結晶が関節や腎臓に残っている場合があります。これをしっかり排出させるには、継続的な治療と尿酸コントロールが不可欠です。また、尿酸が長期間高い状態が続くと、腎障害・尿路結石・動脈硬化・高血圧・心血管疾患など、命に関わる合併症を引き起こす可能性もあります。
尿酸値を安定させることが、痛風の根本治療です
痛風は、一度発症しても正しく治療を続ければ再発を防ぐことができる病気です。
「最近関節が腫れる」「尿酸値が高いと指摘された」など、気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)|痛風について
痛風発作の痛みはどれくらい続きますか?
初回の痛風発作では、激しい痛みが1〜2日続き、その後徐々に和らいで1週間程度で治まることが多いです。ただし、放置していると再発の間隔が短くなり、次第に痛みが長引くようになります。
ビールを飲まなければ痛風にならないのですか?
ビールにはプリン体が多く含まれており、尿酸値を上昇させやすい飲み物の一つです。ただし、ビール以外のアルコールやジュース類も代謝に影響を与えるため、アルコール全般の過剰摂取には注意が必要です。
食事で気をつけるべきポイントは?
以下の点に注意しましょう:
- プリン体の多い食品(レバー・魚卵・エビなど)を控える
- 脂質・糖質の多い食事を減らす
- 水分をしっかり摂る(1日2Lを目安)
- 野菜・きのこ・海藻類などを積極的に摂取する
バランスの取れた食生活が最も重要です。
痛風は完治しますか?
痛風は適切な治療と生活習慣の改善によりコントロール可能な病気です。ただし、治療を中断したり生活習慣が乱れると、再発のリスクが高まります。尿酸値を安定させ続けることが再発予防の鍵となります。
痛みがない時期も通院する必要はありますか?
あります。痛みが出ていない時期にも関節内には尿酸結晶が残っている可能性があるため、数値の改善にかかわらず継続的な治療と通院が必要です。自己判断で治療をやめることは危険です。
痛風かな?と思ったらお早めにご相談ください
痛風は、発作の痛みだけでなく、腎障害や動脈硬化など将来的な健康リスクにも直結する病気です。
「足の指が腫れて激痛が走る」「健康診断で尿酸値が高いと言われた」といった場合は、放置せず早めに整形外科を受診することが大切です。