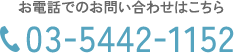足は日常的に体重を支える部位であるため、さまざまな原因によって痛みが生じやすい部位です。足裏・かかと・足の甲・足指・足関節(足首)など、痛みの出る部位によって原因や対処法は異なります。
足は日常的に体重を支える部位であるため、さまざまな原因によって痛みが生じやすい部位です。足裏・かかと・足の甲・足指・足関節(足首)など、痛みの出る部位によって原因や対処法は異なります。
以下のような症状がある場合は、足の骨・関節・靭帯・筋肉・神経などにトラブルがある可能性があります。気になる症状がございましたら、お早めに当院へご相談ください。
このような症状はありませんか?
- 朝起きて最初の一歩が強く痛む(足底腱膜炎の可能性)
- かかとをつくと鋭い痛みがある(アキレス腱周囲の炎症や骨棘の可能性)
- 足の甲が痛くて歩きにくい(疲労骨折・腱鞘炎など)
- 足の裏にしこりのような膨らみや違和感がある(足底線維腫など)
- 足指の付け根が痛い(中足骨頭部痛・モートン病の可能性)
- 足首の外側・内側に痛みや不安定感がある(捻挫・靭帯損傷など)
- 親指のつけ根が赤く腫れている(外反母趾・痛風の可能性)
- 靴に当たって皮膚が痛い(胼胝(たこ)・鶏眼(うおのめ)など)
足の痛みを引き起こす代表的な疾患
足底腱膜炎(そくていけんまくえん)
足底腱膜炎とは、足の裏にある「足底腱膜(そくていけんまく)」という丈夫な線維状の組織に炎症が起こる疾患です。
足底腱膜は、かかと(踵骨)から足指の付け根にかけて足のアーチを支える重要な役割を担っており、歩行やランニング、立ち仕事などによって繰り返し負担がかかることで微細な損傷が起こり、炎症や痛みにつながります。
中高年の女性に多く見られますが、スポーツ愛好者や長時間の立ち仕事をされる方にもよく見られます。
主な症状
- 朝、ベッドから起き上がった最初の一歩で足の裏(かかと付近)に強い痛みがある
- 歩いているうちに一度痛みは軽くなるが、夕方になるとまた痛くなる
- 長時間立っていたり、歩いた後に足裏がズキズキする
- かかとの内側前方を押すとピンポイントで痛い
- 運動やランニングの後に足の裏に違和感が残る
このような症状がある方は、足底腱膜炎の可能性があります。
原因と発症のリスク
足底腱膜炎の主な原因は、足底腱膜にかかる「繰り返しの牽引力」と「微細損傷」による炎症です。以下のような方は特に発症リスクが高くなります
- 長時間の立ち仕事や歩行をされている方
- マラソン・ジョギング・テニスなど足裏に負荷のかかるスポーツをされている方
- 加齢に伴って足底腱膜の柔軟性が低下している方
- 扁平足やハイアーチ(足の甲が高い)など足の構造的な問題がある方
- 体重増加や肥満傾向のある方
診断と検査
診察では、問診と足底の触診を行い、症状の場所や程度を確認します。X線検査や超音波検査を実施し、足底腱膜の状態や骨棘(かかとにできるトゲのような突起)の有無なども評価します。他の疾患(疲労骨折、神経障害など)との鑑別も重要です。
治療方法
保存療法
- 安静・生活動作の見直し
- ストレッチ指導(ふくらはぎ〜足底腱膜の柔軟性改善)
- 足底パッドやインソールによる足底への負担軽減
- 鎮痛薬や湿布の処方
注射療法
局所麻酔薬やステロイド注射を、炎症が強い場合に行うことがあります。
ハイドロリリース(筋膜リリース注射)も行っており、組織間の癒着や滑走不良を改善することで痛みの軽減が期待されます。
→ 1回の注射で改善がみられる方も多くいらっしゃいます。
再発予防・運動療法
痛みが軽減してきた段階で、再発を予防するための運動療法を行います。
特にふくらはぎ・足底の柔軟性と筋力を高めることで、足底腱膜にかかる負担を減らし、再発防止につながります。
アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎
~ふくらはぎからかかとにかけての痛みや違和感を感じていませんか?~
アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎は、かかとの後ろにある太くて強靭な腱「アキレス腱」やその周囲の組織に炎症が起こる疾患です。
走る・跳ぶなどの繰り返し動作によって、腱に微細な損傷が生じることで痛みや腫れを引き起こします。
ランニングやジャンプ動作の多いスポーツ選手や、加齢により腱が硬くなった中高年層に多く見られます。
また、突然運動を始めた方や、硬い靴・不適切な靴を履いている方にも起こりやすい傾向があります。
主な症状
- かかとの後ろやアキレス腱周囲に痛みがある
- 歩き始めや階段の上り下りでふくらはぎの下に違和感がある
- 運動中または運動後にアキレス腱がジンジンする
- 腫れや熱感があり、押すと痛みがある
- 朝の起床時、足首の動きが固く感じる
- ストレッチやジャンプをすると強く痛む
原因について
- ランニング・ジャンプ・急な方向転換などの繰り返し動作
- 準備運動不足やストレッチ不足
- 加齢による腱の柔軟性の低下
- 窮屈な靴や、クッション性の低い靴を長時間使用
- 偏平足やハイアーチなどの足部アライメント異常
- 体重増加や筋力の低下
診断と検査
アキレス腱付着部の石灰化、骨棘(こつきょく:骨のとげ)形成、アキレス腱付着部炎(踵骨の異常)、疲労骨折や関節炎などの他の原因の除外を目的にX線(レントゲン)撮影を行います。
必要に応じて、超音波検査やMRI検査を用いて、腱の肥厚や炎症、損傷の有無を確認します。
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
治療方法
保存療法
- 安静とアイシング:急性期は炎症を抑えるために冷却と安静が基本です。
- ストレッチ指導・リハビリテーション:ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)のストレッチや下腿の筋力トレーニングを行い、再発予防も図ります。
- 足底板(インソール)の処方:アキレス腱にかかる負担を軽減します。
注射療法
局所注射(ステロイドは避けることが多い)
ハイドロリリース(筋膜リリース注射)を適応に応じて行います。周囲の癒着をはがし、腱の滑走性を改善することで、痛みの軽減が期待できます。
PRP療法(自己多血小板血漿注入療法)
当院では、難治性のアキレス腱障害に対してPRP療法も行っております。
自己血液から抽出した血小板を患部に注入することで、組織の修復や炎症の改善を促す治療法です。
特に長期間治りづらい慢性炎症に対して効果が期待されています。
日常生活での注意点
- 運動前後のストレッチを欠かさないようにしましょう
- 靴のフィット感やクッション性にも気を配ってください
- 痛みがある場合は無理をせず、早めに医師の診察を受けることが重要です
モートン病(足指の間の神経の痛み)
モートン病とは、足の中指と薬指の間(第3・4趾間)や、人差し指と中指の間(第2・3趾間)などで、足裏にある靱帯の間を走る神経が慢性的に圧迫されて起こる神経障害です。圧迫された神経が炎症を起こし、足指にしびれや焼けるような痛み(灼熱感)が現れます。
特に中高年の女性に多く、ハイヒールやつま先が細い靴を長時間履くことが一因とされます。足にかかる圧力や体重のかかり方のクセが関係していることもあります。
主な症状
- 足指の付け根(特に第3・4趾間)にピリピリするようなしびれや痛み
- 灼熱感やジンジンとした感覚異常
- 歩くと悪化し、靴を脱ぐと楽になる
- つま先立ちや踏み込む動作で悪化する
- 指の間に異物が挟まっているような違和感
- 症状が進むと、常に神経痛が出現し、じっとしていても痛みを感じることがあります
原因
- ハイヒールや幅の狭い靴による足の圧迫
- 体重の増加や足裏アーチの低下(偏平足傾向)
- 足の構造的な異常や、長時間の立ち仕事・歩行
- ランニングやジャンプを伴うスポーツによる慢性的な刺激
診断と検査
診察では、症状のある部位を圧迫したときにしびれや痛みが再現されるかどうかを確認します。中足骨疲労骨折、関節炎との鑑別目的にX線(レントゲン)検査を行います。必要に応じて、エコー検査(超音波)やMRI検査を行い、神経の腫れや周囲の組織の状態を詳しく調べます。
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
治療方法
保存療法
-
足底板(インソール)やパッドによる足圧の分散
-
靴の見直し(つま先が広く、ヒールの低い靴の着用)
-
消炎鎮痛剤の内服や外用薬
-
神経周囲への注射(ステロイド+局所麻酔薬)
-
ハイドロリリース:神経周囲の癒着を剥がすように生理食塩水などを注入する治療です。症状の改善に効果が期待できます。
多くの方は保存療法で症状が改善しますが、痛みが長期にわたり強く続く場合や、神経腫が大きくなっている場合は、手術(神経の切除または靱帯の切開)を検討することもあります。
中足骨疲労骨折(ランニングや長時間歩行後の甲の痛み)
 「ランニングや長時間の歩行のあと、足の甲がズキズキと痛む」「押すとピンポイントで痛みがある」――このような症状がある方は、中足骨疲労骨折の可能性があります。
「ランニングや長時間の歩行のあと、足の甲がズキズキと痛む」「押すとピンポイントで痛みがある」――このような症状がある方は、中足骨疲労骨折の可能性があります。
中足骨疲労骨折とは、足の甲にある中足骨(ちゅうそくこつ)に繰り返し負荷がかかることで、骨に小さなひび(疲労骨折)が入る状態です。スポーツ愛好家や、硬い靴で長時間歩くことの多い方、体重のかかり方に偏りがある方に多く見られます。
主な症状
- 足の甲(特に第2・第3中足骨付近)にピンポイントの痛みがある
- 歩いたり走ったりすると痛みが悪化する
- 押さえると鋭い痛みを感じる
- 腫れや軽い熱感を伴うことがある
- 初期は我慢できる痛みでも、放置すると悪化して歩行困難になることも
原因とリスク因子
- ランニングやジャンプなど、繰り返しの負荷による骨への微細なダメージ
- 硬い靴や足に合わない靴の使用
- 扁平足や回内足など、足の形状による荷重の偏り
- 骨粗鬆症や栄養不足による骨の脆弱化
診断と検査
問診と触診に加え、X線(レントゲン)検査を行います。初期段階ではX線に写らないこともありますが、痛みの原因を正確に特定するため、まずはX線撮影を行うことが重要です。エコー検査を追加することで見つかるケースもあります。必要に応じて、MRI検査を追加する場合もあります。
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
治療方法
-
基本は安静と患部への負荷軽減が中心となります
-
炎症や痛みが強い場合には、消炎鎮痛薬の使用します
-
歩行時の負荷を減らすために、装具や足底板の使用を検討します
外反母趾(足の親指が小指側に曲がる変形)
外反母趾とは、足の親指(母趾)の付け根の関節が外側に突出し、親指が小指側に「くの字」に曲がる足の変形です。突出した部分に炎症や痛みを伴うことが多く、見た目の変形だけでなく、歩行時の痛みや靴の圧迫感など、日常生活に支障をきたすこともあります。
女性に多く見られ、特にハイヒールやパンプスなどの幅が狭い靴を長年履いてきた方に多くみられますが、遺伝や筋力低下、足の構造的な要因も関係しています。
主な症状
- 足の親指が外側(小指側)に曲がってきた
- 親指の付け根が赤く腫れて、靴に当たると痛い
- 足の甲が広がってきて、靴がきつく感じる
- 長時間歩くと足の親指や足裏が痛む
- 足裏のタコや魚の目が繰り返しできる
原因
- 合わない靴(特にハイヒールや先の細い靴)
- 足のアーチの崩れ(開張足)
- 筋力低下や加齢
- 遺伝的要因(家族に外反母趾の方がいる場合は発症リスクが高まります)
診断と検査
問診・視診に加えて、X線検査を行い、母趾の曲がり具合(外反角)や中足骨の開き具合、関節の変形の程度を確認します。変形の進行度を正確に評価することで、適切な治療方針を決定します。
治療方法
保存療法
-
足底板(インソール):アーチを補正し、圧力の分散や足の正しい使い方を促します。
-
テーピング・外反母趾用装具:親指の角度を矯正し、関節の進行を抑えます。
-
リハビリ・筋力強化:足のアーチを支える筋肉(特に母趾外転筋・後脛骨筋)を鍛えることで、進行抑制が期待されます。
-
薬物療法:炎症や痛みが強い場合は、消炎鎮痛剤や外用薬を使用します。
手術療法
変形が進行し、保存療法では対応できない場合や、日常生活に大きな支障をきたす場合は、骨切り術などの外科的治療が検討されます。当院では対応しておりませんが、必要に応じて専門の医療機関へご紹介いたします。
扁平足(足裏のアーチ低下による痛みや疲労感)
扁平足とは、足の裏に本来あるべき縦のアーチ(土踏まず)が低下または消失した状態を指します。このアーチは、歩行や立位時の衝撃を吸収し、体重をバランスよく支える役割を果たしています。そのアーチが崩れると、足裏への負担が増し、痛みや疲労感、さらには膝や腰への影響も生じることがあります。
主な症状
-
足裏全体が床にベタッとついている
-
少し歩いただけで足が疲れる
-
長時間立っていると足裏やふくらはぎがだるくなる
-
足首の内側が腫れている、または違和感がある
-
靴底の減り方が内側に偏っている
-
スポーツ中や歩行時に膝や腰まで痛くなる
このような症状が続く場合は、扁平足が原因の可能性があります。
扁平足の種類と原因
-
先天性扁平足:生まれつきアーチが形成されていないタイプ。小児期に多く見られます。
-
後天性扁平足:加齢や筋力低下、肥満、足関節の障害などが原因でアーチが崩れていくタイプ。成人以降に増加します。
-
外反扁平足(後脛骨筋機能不全症):内くるぶし付近の腱(後脛骨筋腱)が機能しなくなることで起こる、痛みを伴う進行性の扁平足です。
診断と検査
問診・視診・触診に加えて、X線(レントゲン)検査を行います。足部の骨の配列やアーチの高さ、関節の変形の有無を確認することが可能です。痛みや変形の程度によっては、立位と荷重下での撮影が必要となります。
※症状が軽度であっても、他の疾患(疲労骨折や変形性足関節症など)との鑑別のため、X線検査は非常に重要です。
治療方法
保存療法が基本です。足底アーチを支えるためのインソール(足底板)や靴の見直しを行います。
痛みや炎症が強い場合は薬物療法も併用します。
運動療法により、足のアーチを支える筋肉(特に後脛骨筋や足底筋)の強化を行います。
痛風発作(足の親指のつけ根が突然腫れて激しく痛む)
痛風は、血液中の尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が続くことで、体内に尿酸の結晶が蓄積し、それが関節内に沈着して炎症を引き起こす病気です。特に多いのが足の親指のつけ根(母趾基部)の関節で、ここに強い痛みと腫れを伴う「痛風発作」が起こります。
痛風は男性に多く、30~50代の働き盛りの世代によく見られます。プリン体の多い食事(肉・魚卵・アルコールなど)、ストレス、過労、水分不足などが発作の引き金となることもあります。
主な症状
-
足の親指のつけ根が突然腫れて、赤くなっている
-
触れるだけでも激痛が走る
-
発熱を伴うような関節の腫れがある
-
朝起きた時から急に関節が痛み出した
-
数日で痛みが治まったが、再び繰り返す
このような症状がある場合、「痛風発作」の可能性があります。突然の激痛で、靴を履くことも困難になることが多いため、早期の受診と治療が重要です。
原因と病態
-
高尿酸血症:尿酸値が7.0mg/dLを超えると、関節や腎臓に尿酸が結晶化しやすくなります。
-
尿酸結晶の沈着:関節内にたまった尿酸結晶が免疫細胞によって攻撃され、激しい炎症が引き起こされます。
-
好発部位:特に冷えやすい関節(足の親指のつけ根など)で発症しやすく、夜間~明け方にかけて発作が起こることが多いです。
診断と検査
問診と診察により、痛みの部位や発症経緯を確認します。
X線検査を行い、関節の破壊や他の疾患(感染・変形性関節症など)との鑑別を行います。初期の痛風ではX線所見が乏しいこともありますが、念のために画像評価を行うことが望ましいです。
血液検査で尿酸値の確認などを行います。
治療方法
急性発作時の対応
消炎鎮痛薬(NSAIDs)の内服により、炎症と痛みを抑えます。
痛みが強い場合には、ステロイドの内服や関節内注射を行うこともあります。
局所の冷却と安静が重要です。無理に動かさず、足を心臓より高く上げて休めましょう。
発作が治まった後
尿酸値を下げる薬(尿酸降下薬)の内服を開始し、再発を予防します
生活習慣の見直し:プリン体の多い食品や過度なアルコール摂取を控え、適度な運動と十分な水分摂取を心がけることが大切です。
放置しているとどうなる?
痛風発作を繰り返すと、関節が変形したり、尿酸結晶が皮下に塊(痛風結節)として現れることがあります。また、腎臓に沈着することで腎機能障害や尿路結石などの合併症を引き起こすこともあります。
足関節捻挫・靭帯損傷(足首をひねった・内出血・腫れ・痛み)
足関節捻挫は、足首をひねったり、段差や傾斜でバランスを崩したりすることで起こる、最も身近な外傷のひとつです。特に多いのは、内側にひねる「内反捻挫」で、足首の外側の靱帯(前距腓靱帯など)が伸びたり断裂したりすることで強い痛みや腫れが生じます。
スポーツ中だけでなく、日常生活での転倒や段差の踏み外しでも起こるため、年齢や性別に関係なく誰にでも起こり得る疾患です。軽い捻挫と思って放置すると、靱帯がゆるんだまま不安定性が残り、「クセになる」こともあります。
主な症状
-
足首をひねってから痛みが引かない
-
足首の外側が腫れている、内出血している
-
痛みで体重がかけられない、歩きづらい
-
何度も足首をひねくり返してしまう
-
スポーツ中に足首を捻ってからプレーに支障がある
このような症状がある場合は、足関節の靱帯損傷の可能性があります。早期の適切な処置が、後遺症や再発防止のカギとなります。
診断と検査
視診・触診により、腫れ・圧痛・不安定性を評価します
X線(レントゲン)検査で骨折の有無を確認します
超音波検査(エコー)で靱帯の損傷の程度や関節内の出血を評価することもあります
症状や所見に応じて、MRI検査で詳しく精査することもあります
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
治療と検査
急性期(受傷直後〜数日)
RICE処置(Rest:安静、Ice:冷却、Compression:圧迫、Elevation:挙上)を徹底します
必要に応じて、固定(テーピングやサポーター、装具、シーネ)を行います
消炎鎮痛薬(内服や外用)の処方も可能です
回復期(数日〜数週間)
徐々に可動域訓練・バランス訓練・筋力トレーニングを開始し、再発予防に努めます
理学療法士によるリハビリテーションも受けていただけます
中等度以上の損傷では、装具の使用期間の調整や段階的な運動復帰プログラムを組んでサポートします
放置するとどうなる?
「軽い捻挫だから」と処置せず放置すると、靱帯がゆるんだままとなり足関節の不安定性が残ることがあります。これにより、
-
何度も捻挫を繰り返す(習慣性捻挫)
-
慢性的な腫れや痛みが続く
-
関節軟骨の損傷や変形性関節症に進行
といったリスクが高まります。
有痛性外脛骨(足の内側の出っ張りや痛み)
有痛性外脛骨とは、足の内側(内くるぶしの下あたり)にある「外脛骨(がいけいこつ)」という余分な骨が痛みを引き起こす疾患です。外脛骨は約15~20%の方に存在するとされる先天的な副骨で、普段は痛みがないものの、成長期や運動の負荷などをきっかけに炎症を起こし、痛みが出ることがあります。
特に10代の女性やスポーツをしているお子さんに多く見られる傾向があります。
主な症状
- 足の内側に出っ張りがある
- 運動のあとに足の内側が痛む
- 靴に当たって足の内側が赤くなり痛い
- 歩行や走るときに痛みが出る
- 足のアーチが崩れている(扁平足気味)
これらの症状がある場合は、有痛性外脛骨の可能性があります。
原因
外脛骨は、足の内側にある舟状骨(しゅうじょうこつ)という骨の内側に存在する副骨です。以下のような要因で痛みが出やすくなります。
- 成長期の骨の未完成(10代に多い)
- 扁平足(足のアーチが低下し、外脛骨に負担がかかる)
- 運動による過度な負荷(ジャンプ、ダッシュなど)
- 靴による圧迫や摩擦
診断と検査
視診・触診で、足の内側の突出部位の圧痛や腫れを確認します
X線(レントゲン)検査では、外脛骨の有無・形状・骨の癒合状態などを確認します
→ 外脛骨のタイプ(Type I~III)により治療方針が変わることがあります
必要に応じてMRI検査を行い、骨の炎症や周囲組織の状態を詳しく評価します
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
治療方法
有痛性外脛骨の多くは、保存療法(手術をしない治療)で症状が改善します。
保存療法
-
運動の制限・安静(特にジャンプやダッシュ動作)
-
インソール(足底板)やアーチサポーターの使用
→ 扁平足を補正し、舟状骨への負担を軽減します -
湿布や内服薬などの消炎鎮痛薬
-
テーピングや足関節の装具による局所の安定化
-
ストレッチ指導(ふくらはぎや足底の柔軟性を改善)
注射療法
痛みが強い場合や急性炎症を伴う場合には、局所麻酔薬やステロイドを併用した注射を行うことがあります。
足根管症候群(そっこんかんしょうこうぐん)
足根管症候群は、内くるぶしの下を通る「後脛骨神経」が圧迫されて起こる神経障害です。足根管とは、内くるぶしの下から足の裏にかけてのトンネル状の構造で、神経・血管・腱などが通っています。何らかの原因でこの管内が狭くなると、神経が圧迫されて足の裏に痛みやしびれが現れます。
ランニング、長時間の歩行、外反扁平足、ガングリオン、外傷後の瘢痕などが原因となることが多く、男女問わず幅広い年代で見られます。
主な症状
- 足の裏がじんじん・ビリビリとしびれる
- 内くるぶし周辺を押すと痛みやしびれが強くなる
- 足の裏が焼けるように痛い(灼熱感)
- 立ちっぱなしや長時間歩くと痛みが悪化する
- 足の裏の感覚が鈍い、異常な感覚がある
- 足の裏や足指に力が入りにくい
これらの症状がある場合、足根管症候群の可能性があります。放置すると、しびれや感覚障害が強まり、足の機能に支障をきたす恐れもあります。
原因
足根管症候群の原因は以下のようにさまざまです。
- ガングリオンや腫瘍による圧迫
- 足関節の捻挫・骨折後の瘢痕組織
- 外反扁平足による後脛骨神経への牽引
- 糖尿病などの代謝性疾患による神経脆弱性
- 足関節の過度な使用や炎症
- 腫れや浮腫による足根管内圧の上昇
診断と検査
チネル徴候(内くるぶし付近を軽く叩くと足裏にしびれが走る)が陽性になることがあります。
-
X線(レントゲン)検査:骨の変形や扁平足の有無、外傷の有無を確認します。
-
エコー検査:ガングリオンや腫瘍、滑液包の腫れなどの有無を確認できます。
-
MRI検査:神経や周囲組織の状態をより詳細に評価するために行うことがあります。
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) -
神経伝導速度検査(必要に応じて):神経の伝わりやすさを調べ、診断の補助とします。
治療方法
足根管症候群の多くは、保存療法によって症状の改善が期待できます。
保存療法
- 安静・運動制限
- 足底板(インソール)の使用:アーチを補正し神経への負担を軽減します
- 消炎鎮痛薬の内服・外用(湿布など)
- 理学療法(ストレッチ・温熱・電気治療など)
- ハイドロリリース注射:神経の滑走性を高め、癒着を剥がすことで神経圧迫を改善します
- ステロイド注射:炎症が強い場合に行います(頻用は避けます)
リスフラン関節捻挫
足の甲にあるリスフラン関節(中足部)に生じる捻挫で、見逃されやすく、重症化することもある足のケガです。
リスフラン関節は、足の甲の中ほどに位置する「中足骨」と「足根骨」をつなぐ関節です。この部分に強い外力が加わることで、関節や靭帯に損傷が起こる状態を「リスフラン関節捻挫」と呼びます。
ジャンプの着地、転倒、交通事故、重い物を足の上に落とすなどが原因となりやすく、スポーツ選手から一般の方まで幅広く発症します。
主な症状
- 足の甲に痛みや腫れがある
- 足の甲を押すと強く痛む
- 体重をかけると足の甲が痛む
- 足を地面につけるだけで痛く、歩くのがつらい
- 受傷直後よりも、時間が経つにつれて痛みが強くなった
- 足の裏がしびれる、感覚が鈍い
- 足の形が左右で違う気がする
このような症状がある場合は、リスフラン関節捻挫の可能性があります。
原因とメカニズム
リスフラン関節捻挫は、以下のような状況で起こりやすいとされています。
- ジャンプの着地時に足を捻った
- 階段や段差でバランスを崩して転倒した
- 足の甲を踏まれた・重い物を落とした
- サッカー・ラグビー・バスケットボールなどの接触スポーツ
これらの衝撃により、中足骨と足根骨をつなぐ靭帯や関節包が損傷し、関節が不安定になることがあります。損傷が大きいと、骨同士がズレる「リスフラン関節脱臼骨折」に進行する場合もあります。
診断と検査
当院では、リスフラン関節捻挫の正確な診断のために、以下のような検査を行っています。
-
腫れや圧痛、関節の不安定性の有無を確認します。
-
X線(レントゲン)検査:骨のズレや骨折の有無を確認します。左右比較撮影を行うこともあります。
-
エコー検査:靭帯損傷の有無や腫脹の程度を観察できます。
-
CT・MRI検査(必要に応じて):微細な骨折や靱帯損傷、軟部組織の状態を詳細に確認します。
(当院ではCT・MRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
CT・MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
治療方法
保存療法
- 安静・アイシング・圧迫・挙上(RICE処置)
- 足底装具(インソール)やギプス固定:関節の安定性を保ちつつ、炎症を抑えます。
- 松葉杖などによる免荷:負荷をかけないことで靱帯の治癒を促します。
- 消炎鎮痛剤・湿布などの内服・外用薬
- リハビリテーション:腫れが引いてきた段階で可動域訓練や筋力強化を行います。
注射治療
- ハイドロリリース注射:靱帯周囲の滑走障害が疑われる場合に、エコーガイド下で行います。
- 局所麻酔薬+ステロイド注射:炎症や腫れが強い場合に使用します。
手術治療(重度の場合)
靱帯断裂や関節の不安定性が強い場合、靱帯再建術やスクリュー固定術などの手術が必要になることもあります。当院では手術が必要と判断された際には、専門医療機関をご紹介いたします。
シーバー病(踵骨骨端症)|子どものかかとの痛み
シーバー病(踵骨骨端症)は、成長期の子どもに多く見られるかかとの骨(踵骨)の成長軟骨部分に炎症が起こる疾患です。特に小学校高学年から中学生頃の、活発にスポーツをしているお子さまに多く発症します。繰り返されるジャンプやダッシュなどの動作により、踵骨の骨端部(成長板)に過度な負荷がかかることで発症します。
スポーツ活動量が多い時期に発症しやすく、バスケットボール・サッカー・陸上競技などをしている子どもに頻発します。
主な症状
- 運動時や運動後のかかとの痛み
- 歩行時の違和感や軽いびっこ(跛行)
- かかとを押すと痛がる(圧痛)
- 朝よりも夕方の方が痛みが強くなる傾向があります。
- 特に両足同時ではなく、片足だけに症状が現れることが多いのも特徴です。
診断と検査
診断は問診と理学所見を中心に行いますが、骨の異常や骨折との鑑別のためにX線(レントゲン)検査を行います。X線では、踵骨の成長軟骨に炎症の兆候があるかを確認します。その他、必要に応じて超音波(エコー)検査を行うこともあります。
治療方法
基本的には保存療法(手術を伴わない治療)が中心です。
- 一時的な運動の中止または制限
- アイシングや湿布による炎症の抑制
- ストレッチやリハビリによるアキレス腱やふくらはぎの柔軟性改善
- 必要に応じて足底板(インソール)などを使用して足への負担を軽減します。
多くの場合、成長とともに自然に改善することが多い疾患です。一度当院でご相談ください。