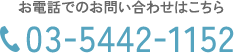肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)について
— 肩が上がらない・夜間の肩の痛みにお悩みの方へ —
四十肩・五十肩とは?
 四十肩・五十肩とは、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれる疾患です。名前の通り、40代・50代を中心とした中高年層に多く見られるため、こうした俗称で広く知られています。
四十肩・五十肩とは、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれる疾患です。名前の通り、40代・50代を中心とした中高年層に多く見られるため、こうした俗称で広く知られています。
この病気では、肩の関節を構成する関節包・靱帯・腱板・滑液包などの周囲組織に炎症や損傷が起こり、肩の動きに痛みが伴うようになります。特に、腕を上げる・後ろに回すといった動作が制限される運動障害や、就寝中の夜間痛が大きな特徴です。
「肩こり」と混同されやすい症状ですが、四十肩・五十肩は関節の可動域制限を伴う病気であり、放置すると関節が固まる(拘縮)リスクがあります。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の主な症状
このような症状があればご相談ください
- 肩が痛くて腕が上がらない・後ろに回らない
- 洋服を着る・髪を結ぶ動作がつらい
- 夜寝ているときに肩がズキズキ痛む(夜間痛)
- 肩が固まって動かない
- 片側だけだった痛みが、数ヶ月後に反対側にも出てきた
こうした症状は、肩関節周囲炎のサインかもしれません。早期に診断・治療を行うことで、症状の悪化や長期化を防ぐことができます。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の進行と経過
肩関節周囲炎は、症状の進行に応じて3つの段階に大別されます。放置したままで適切な治療を行わない場合、関節の動きが制限され、やがて肩が固まってしまう恐れもあります。
治療を開始すれば多くの場合は半年ほどで改善が見込まれますが、症状が重いケースでは回復に1年程度かかることもあります。
急性期(発症から数週間~2ヶ月程度)
最も炎症が強く現れる時期です。肩から腕にかけて鋭い痛みが生じ、腕を動かすのが困難になることもあります。特に就寝中の痛みが強く、眠りを妨げるほどになるケースもあります。
慢性期(拘縮期:2〜6ヶ月程度)
安静時には痛みが和らぐものの、筋肉や腱のこわばりが残り、関節の可動域が狭くなります。腕を上げたり後ろに回したりする動作で痛みが出るのが特徴です。このように関節が固まった状態を「肩関節拘縮」と呼びます。
回復期(6ヶ月以降)
徐々に関節の可動域が広がり、腕の動きも改善されていきます。治療を継続することで、半年ほどで日常生活に支障がないレベルまで回復することが多いですが、症状が強い場合は1年ほどかかることもあります。
肩関節周囲炎の検査
X線(レントゲン)検査と鑑別
四十肩・五十肩そのものはX線では明確な異常が映らないことが多いですが、以下の疾患との区別が重要です:
- 腱板断裂(肩の腱が切れてしまう病気)
- 石灰沈着性腱板炎(石灰が肩にたまり激痛を伴う)
- 関節リウマチや変形性関節症などの全身疾患
当院では、X線検査やエコー検査などを適切に組み合わせて診断を行っています。
(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。
MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の治療
薬物療法
- 消炎鎮痛薬(NSAIDs):飲み薬・貼り薬・注射などで炎症を抑え、痛みを軽減します。
- 筋弛緩薬:肩周囲の筋肉の緊張を緩めて可動域を改善します。
- ステロイド注射:炎症が強い場合は、関節内や滑液包への注射が有効です。
- ヒアルロン酸注射:関節の動きを滑らかにする潤滑剤として使用することもあります。
ハイドロリリース(筋膜リリース注射)
当院では、肩関節周囲の筋膜の癒着や神経周囲の滑走不良に対し、超音波ガイド下に生理食塩水などを注入する「ハイドロリリース(筋膜リリース注射)」を積極的に導入しています。
夜間痛や可動域制限の改善、血流促進に有効とされ、副作用の少ない治療法です。
理学療法(リハビリ)
- ストレッチ・関節可動域訓練:理学療法士が一人ひとりに合わせたプログラムを提案し、関節の動きを改善します。
- 筋力トレーニング:肩周囲の筋力バランスを整えることで再発防止を図ります。
自宅でのセルフケア指導
通院だけでなく、日常生活の中でも継続的なケアが重要です。
当院では、症状に合わせた自宅でできるストレッチや運動、日常動作の工夫についても丁寧にご案内しています。